ヨーロッパ株に興味はあるけれど、「実際に儲かるの?」「失敗した人も多いのでは?」と不安に思っていませんか?
本記事では、実際にヨーロッパ投資で成功した投資家・失敗した投資家の“実例5選”を紹介します。
有名な投資家たちの選択から見えてくる「勝てる投資の共通点」、そして避けるべき「典型的な失敗パターン」まで、リアルな事例とともに解説!
ヨーロッパ株に初めて挑戦する方も、すでに運用している方も、この記事を読むことでより確かな判断軸を持てるようになります。
ヨーロッパ投資とは?なぜ今注目されるのか
これまで多くの日本人投資家は、日本株や米国株に投資の軸足を置いてきました。しかし今、静かに注目を集めているのが「ヨーロッパ投資」です。
ヨーロッパは、伝統ある産業と最先端のイノベーションが共存する地域であり、エネルギー・自動車・ラグジュアリー・製薬・再エネといった多様なセクターに強みを持つ国が集まっています。欧州中央銀行(ECB)の政策やEU単位の規制も投資環境に大きな影響を与えるため、米国や日本とは異なる動きを見せる地域分散先としても非常に魅力的です。
以下では、日本や米国中心の投資ではリスクが集中する理由と、ヨーロッパ市場の基本構造について詳しく解説します。
日本株・米国株だけでは危険?分散先としての欧州
「分散投資が重要」とよく言われますが、実際には多くの個人投資家が日本株と米国株に偏ったポートフォリオを組んでいます。これは地理的・経済的リスクを抱えやすく、特定の市場の不調がそのまま資産全体に響くというリスクを孕んでいます。
そこで浮上するのが「ヨーロッパ株」という選択肢です。
たとえば、アメリカのハイテク株が金利上昇で不安定になった場合でも、欧州のディフェンシブ株や高配当銘柄が相対的に強さを見せる場面もあります。また、日本では得られないユーロ建て資産の分散効果も得られるため、為替リスクを味方にできる可能性もあります。
さらに、近年はESG投資やグリーンディール政策を背景に、欧州企業の一部が新たな成長トレンドを牽引しています。これは中長期でのリターン獲得にもつながる要素です。


ヨーロッパ市場の基本構造と主な取引所
ヨーロッパ投資を検討する際に知っておきたいのが、市場の構造と取引所の特徴です。ヨーロッパといっても単一の市場ではなく、以下のような主要取引所を中心に構成されています。
- ユーロネクスト(Euronext):パリ、アムステルダム、ブリュッセルなど複数国の市場が統合。多国籍企業や高配当銘柄が多数上場。
- ドイツ証券取引所(Xetra/フランクフルト):シーメンスやBASFなど、欧州産業の中核企業が集結。
- ロンドン証券取引所(LSE):ブレグジット後も世界有数の国際市場として存在感。ETFやADRも豊富。
- スイス証券取引所(SIX):ネスレ、ノバルティス、ロシュといったグローバル企業が上場。スイスフラン建て資産としての分散効果も。
また、ヨーロッパには単一通貨ユーロ圏と非ユーロ圏の国々が混在しており、通貨の選択も投資成績に影響を与えます。たとえばスイス株はスイスフラン建て、英国株はポンド建てという形で、通貨分散によるヘッジ効果も得られます。
このように、ヨーロッパ投資は一見複雑に思えますが、正しく理解すれば米国株とは異なる価値軸を持つ、優れた分散投資先になるのです。
過去の成功事例から学ぶヨーロッパ投資の魅力
ヨーロッパ株は地味だと思われがちですが、実は世界中のプロ投資家たちが着実に資産を増やしてきたフィールドです。ここでは、3つの代表的な成功事例を紹介し、ヨーロッパ投資の具体的な魅力を掘り下げます。
【実例:テリー・スミス】NestléやL’Oréalに見る欧州消費株の底力

ヨーロッパ株投資の現実的な成功例として、無視できない存在がイギリスのファンドマネージャー、テリー・スミス(Terry Smith)です。彼が運用する「Fundsmith Equity Fund」は、2010年から年率10%を超えるリターンを継続的に実現しており、プロ・個人問わず世界中の投資家から高い信頼を得ています。
注目すべきは、彼のファンドの中核に位置するのがヨーロッパのグローバル消費企業である点です。
なぜテリー・スミスは欧州株を選ぶのか?
彼の基本方針は明確です。「高品質のビジネスを適正な価格で購入し、極力売らずに保有し続ける」。この哲学のもと、スミス氏は一貫して以下のような企業を重視しています:
- 強力なブランド力を持つ
- 世界中に販売網があり、地域リスクを分散できる
- 継続的な利益成長が見込める
- ROCE(資本利益率)が高く、経営効率に優れる
これらを満たす代表格が、Nestlé(スイス)やL’Oréal(フランス)といった欧州のグローバル消費株なのです。
投資銘柄① Nestlé(ネスレ):世界最大の食品企業
スイスに本社を置くNestléは、コーヒーのネスカフェやミネラルウォーターのペリエ、ペットフードのピュリナなど、日常生活に密着したブランドを多数保有しています。
テリー・スミスはこの企業を、典型的な「売上が安定し、利益率が高く、イノベーションを怠らない理想企業」と評価。Nestléは約190カ国で事業展開しており、地域・通貨リスクを自然に分散できるグローバルな守備銘柄としても機能します。
特に注目すべきは、近年のNestléが食品テック分野(植物由来食品や機能性食品など)にも積極投資を行っており、成熟企業でありながら成長性も兼ね備えている点です。
投資銘柄② L’Oréal(ロレアル):圧倒的なブランドの壁(モート)
L’Oréalはフランスを代表する化粧品企業で、LancomeやKiehl’s、Maybellineなど価格帯の異なる複数ブランドを展開しています。
スミス氏は、L’Oréalが持つ「ブランドの壁(経済的な堀)」の強さに注目しています。
化粧品業界は広告投資が激しく新興勢力が参入しやすい分野ですが、L’Oréalは研究開発力と販売ネットワークを通じて“価格競争に巻き込まれない高収益体質”を構築しています。
加えて、新興国市場への展開とeコマース対応を加速しており、グローバル需要の取り込みにも成功しています。
テリー・スミスの投資戦略に学ぶ:長期・集中・質へのこだわり
Fundsmithの特徴は、「20〜30銘柄に厳選投資し、めったに売らない」という集中投資スタイルです。
彼の言葉を借りれば、「売買で儲けようとするのではなく、“持ち続ける価値のある企業”を選び抜くのが仕事」だと語っています。
NestléやL’Oréalのように、一度ポートフォリオに加えれば10年単位で保有し、複利効果を最大化する。これは個人投資家でも再現可能なアプローチです。
このように、ヨーロッパ市場にはスミス氏が好むような“守りながら成長する優良企業”が数多く存在しており、長期・質重視の投資スタイルとの親和性が非常に高いことが分かります。
【実例:ノルウェー政府年金基金】再エネセクターに資金を集中(Orsted、Vestasなど)

ヨーロッパ投資のもう一つの成功モデルが、ノルウェー政府年金基金(Government Pension Fund Global)による再生可能エネルギー企業への戦略的投資です。
同基金は、運用資産額が世界最大規模(2024年時点で約1.6兆ドル)を誇り、グローバル投資家からも注目されている存在です。とりわけヨーロッパ株式においては、ESG(環境・社会・ガバナンス)要素を重視しつつ、再エネ関連株で成果を上げてきた実績があります。
投資対象①:Orsted(デンマーク)―世界最大の洋上風力企業
Orstedはもともとデンマークの国営石油・ガス会社でしたが、2010年代から事業を急速に転換し、洋上風力発電に特化した再エネ企業へと完全にシフトしました。
ノルウェー政府年金基金はこの企業の成長性と政策連動性に注目し、早期から資金を投じることで中長期的なリターンを得てきました。
- 欧州全体の洋上風力発電容量の約3割をOrstedが保有(2023年時点)
- グリーンディール政策・各国のカーボンニュートラル政策と強い連動
- 規模の経済と技術優位性により、再エネ分野で高い収益性を確保
Orstedは単なる「再エネ企業」ではなく、政策と市場の両面から評価される“ESGの優等生”といえます。
投資対象②:Vestas(デンマーク)―風力タービンのグローバルリーダー
もう一社、ノルウェー政府年金基金が積極的に投資してきたのが、風力タービン製造で世界最大級のシェアを持つVestas Wind Systemsです。
Vestasはハードウェア供給に加え、メンテナンスや予知保全などのサービス領域にも進出しており、収益の多角化と安定化を進めています。
- 世界80カ国以上で風力タービンを展開
- 自社の技術革新力とパートナー戦略が業界をリード
- 発電企業との長期契約により安定的な売上基盤を構築
同社への投資は、再エネ産業のインフラ面にアプローチする形で、Orstedとは異なる投資戦略を実現しています。
■ ESG重視の運用がリターンにつながった理由
ノルウェー政府年金基金は単なる道徳的理由でESG投資をしているわけではありません。むしろ、
「持続可能な企業こそ長期的に優れた投資対象である」というデータ主導の信念に基づいています。
この視点は、以下のような理由でヨーロッパ市場に非常にマッチします:
- 欧州は世界でも最も環境規制と脱炭素政策が進んでいる地域
- 国レベルでの再エネ導入目標が明確かつ高水準
- グリーン関連企業に対して資金・税制・制度支援が厚い
これにより、ESG=低リターンという旧来の認識を覆し、成長性と収益性の両立が可能な“攻めの投資領域”として機能しているのです。
【実例:ジャン=マリー・エヴェイヤール】欧州の割安優良株を見極める長期投資術

欧州株における「長期・価値重視」の投資スタイルで成功を収めた代表格が、
フランス出身の著名バリュー投資家ジャン=マリー・エヴェイヤール(Jean-Marie Eveillard)です。
彼は1979年から2004年までの25年間、米国のFirst Eagle Global Fund(旧SoGen International Fund)を率い、年平均15.7%の驚異的なリターンを実現しました。
特筆すべきは、このファンドの中核にヨーロッパの割安株や中小型株、家族経営企業が多く含まれていた点です。
割安で放置された“隠れた名企業”に注目
エヴェイヤールの投資哲学は、ベンジャミン・グレアム流のクラシックな価値投資に根ざしています。
企業の内在価値を厳密に分析し、それを大幅に下回る価格で市場に放置されている銘柄をコツコツ拾っていくスタイルです。
彼が好んだのは以下のような企業群です:
- 時価総額が小さく、メディアに取り上げられない欧州企業
- 一族経営で、経営の安定性と保守的な資本政策を持つ企業
- 地方に根ざし、競合の少ないニッチ市場を独占している企業
- グローバル展開していないが、地域内で強いブランドを持つ企業
これらの企業は、短期的には市場の関心を集めにくいものの、本質的な収益力や資産価値を持ち、長期では大きなリターンを生むことがあると彼は考えていました。
欧州投資家の盲点を突いた逆張り戦略
エヴェイヤールが特に成功したのは、欧州市場がバブル・過熱感に包まれていた時期に投資を控え、逆に見捨てられていた割安株に集中した点です。
例えば1990年代、ITバブルで欧州のグロース株が過熱した際、彼はそれらを完全に回避し、地味だが財務体質が堅固な企業に資金を振り向けることでバブル崩壊後も高いリターンを維持しました。
また、ドイツやフランスの地方企業の中には、有形固定資産や現預金が豊富で実質PBRが1.0を切るような“眠れる資産株”も多く、彼はそれらを早期に発掘・保有し続けました。
投資家への教訓:ヨーロッパの“地味な優良株”こそ狙い目
ジャン=マリー・エヴェイヤールの手法は、派手さはないものの、以下のような投資家にとって極めて有効です。
- 米国ハイテク株の高ボラティリティに疲れた人
- 長期保有を前提に、年5〜10%の堅実なリターンを狙いたい人
- ヨーロッパのローカル企業に価値を見出したい人
欧州にはLVMHやNestléのようなメガ企業だけでなく、バリュエーションが放置された“知る人ぞ知る銘柄”が多数存在します。
それらを長期視点で丁寧に見つけ出し、マーケットが正当に評価するまで保有し続けるというエヴェイヤールの姿勢は、個人投資家にも十分に再現可能な戦略と言えるでしょう。
苦い失敗例に学ぶ、ヨーロッパ投資の落とし穴
どんな投資にもリスクはつきものです。ヨーロッパ株も例外ではありません。
むしろ、制度の違いや政治的リスク、通貨要因など、海外ならではの落とし穴が存在します。
この章では、実際に多くの投資家が損失を被った3つの失敗事例を取り上げ、欧州投資で避けるべきポイントを解説します。
【実例:ジョージ・ソロス】ユーロ導入初期のイタリア国債への過剰なポジション取り
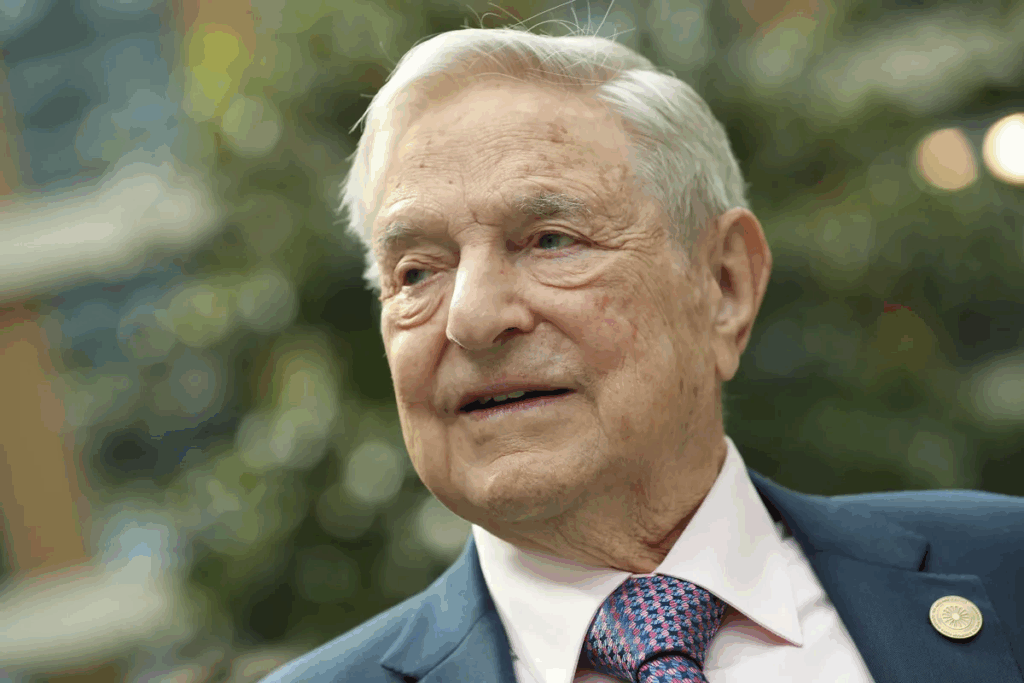
世界屈指の投資家ジョージ・ソロスが手がけたユーロ初期の欧州債券投資は、ヨーロッパ金融市場の不確実性を示す重要な失敗事例として今なお語り継がれています。
とりわけ、イタリア国債への過剰なポジション取りとその結果は、ユーロ統合に過度な楽観を持ったリスク管理の甘さを浮き彫りにしました。
背景:ユーロ誕生と「収束トレード」への期待
1999年、ユーロという共通通貨が導入され、域内各国の金利差は次第に縮小するとの期待が高まりました。これに乗じ、多くのヘッジファンドが“収束トレード”と呼ばれる戦略を取り始めます。
この戦略は、財政状況の不安定な国(例:イタリア、ギリシャ)の国債利回りが、ドイツのような信用度の高い国の水準に近づくと見込み、スプレッドが縮小することに賭けてイタリア国債を買うというものです。
ジョージ・ソロスもこの収束トレードに大きなポジションで参入しました。
ユーロ圏としての統一経済、ECBの設立、通貨統合――こうした材料が投資家に“国家リスクが薄れる”という誤った安心感を与えていたのです。
想定外の展開:イタリアの構造的リスクが浮上
しかし、統一通貨の導入だけで国ごとのリスクが消えるわけではありませんでした。イタリアは以下のような構造的課題を抱えていたのです:
- 高水準の財政赤字と累積債務
- 経済成長率の停滞と労働市場の硬直性
- 非効率な官僚制度と腐敗問題
これらの根本問題はユーロ導入後も解決されず、むしろ金利政策を自国でコントロールできなくなったことで、経済政策の柔軟性が低下。
その結果、イタリア国債は売られ、利回りは上昇。ソロス率いるファンドも大きな評価損を抱えることになりました。
教訓:欧州投資では「通貨統合=信用統合」ではない
この失敗事例から学べる最大の教訓は、表面的な統合(ユーロ導入)に惑わされず、各国の実態に目を向けることの重要性です。
欧州ではユーロ圏といえども、財政・政治・構造改革のスピードは国ごとに大きく異なります。
イタリア、スペイン、ギリシャといった周縁国は、同じ通貨圏にあってもリスクプレミアムを常に内包しているのです。
個人投資家が欧州債券やETF、ユーロ建てファンドに投資する際も、単に「欧州=一枚岩」と考えず、国別リスクの本質を見極める目が不可欠です。
【実例:英国ファンド】ブレグジットで資金流出、ウッドフォード・ファンドの破綻

ヨーロッパ投資における最大の政治リスク事例のひとつが、2016年のイギリスのEU離脱(ブレグジット)です。
この出来事により、イギリス市場に強く依存していた複数のファンドが大きな打撃を受け、なかでも象徴的だったのがウッドフォード・エクイティ・インカム・ファンドの破綻です。
このケースは、政治的イベントが金融市場をどう揺るがすかを如実に示した失敗事例であり、個人投資家にも重要な示唆を与えます。
ブレグジットが市場に与えた衝撃
2016年6月の国民投票でイギリスのEU離脱が決定した瞬間、英ポンドは急落し、株式市場も大きく混乱しました。
当初は「まさか離脱にはならないだろう」と楽観視されていたため、想定外の結果に対応できなかったファンドが多く、資金流出が一気に加速しました。
特に打撃を受けたのは、以下のような特徴を持つファンドです:
- 英国内の中小型株に集中していた
- 英ポンド建て資産に偏っていた
- 流動性の低い未公開株や小型株を多く組み込んでいた
この条件をすべて満たしていたのが、ウッドフォード・ファンドでした。
ウッドフォード・ファンド破綻の経緯
ニール・ウッドフォードはかつて英国で最も有名なファンドマネージャーの一人であり、長年にわたって高い実績を残してきました。
しかし、彼が立ち上げたウッドフォード・エクイティ・インカム・ファンドは、ブレグジット以降の英中小株の低迷に直撃され、運用資産が急激に縮小。
特に問題視されたのは、未上場株や流動性の低い資産を組み入れすぎた結果、解約に対応できずに資金を凍結せざるを得なかった点です。
2019年にはファンドが正式に運用停止、投資家の多くは資金の大半を失う結果となりました。
投資家が学ぶべきポイント
この破綻事例から得られる教訓は3つあります。
- 政治リスクを軽視しないこと
政治的イベントは予測困難かつ破壊力が大きい。特に通貨と国境をまたぐ投資においては要注意。 - 流動性のない資産は致命傷になり得る
マーケットが不安定になるときこそ「すぐ売れるかどうか」が問われる。 - 過度な集中投資はリターンを狙う半面、下振れリスクも倍増する
地域、セクター、通貨の分散はあくまで“守り”の基本戦略。
ブレグジットは、投資家にとって「政治は無視できないファンダメンタルズの一部である」ことを改めて突きつけました。そしてウッドフォード・ファンドの崩壊は、「名声あるマネージャーでも誤ることがある」という冷徹な現実を示しています。
【実例:高配当ETFが招いた悲劇】減配・格下げ・暴落のトリプルパンチ
ヨーロッパの高配当株に魅力を感じ、ETFを通じて分散投資したつもりが、「減配 → 格下げ → 株価暴落」という三重苦に巻き込まれる。
このような痛ましい失敗例は、実際に多くの個人投資家を直撃しました。特に象徴的なのが、イタリアの通信大手Telecom Italia(ティム)を含む欧州高配当ETFの事例です。
高配当の誘惑に個人投資家が殺到
Telecom Italiaは長らく「高配当株」の代表格として認識されていました。
2015年頃から徐々に配当を再開し、利回りは一時6〜7%に達するなど、欧州配当ETFの中核銘柄としても数多く組み込まれてきました。
このような利回りに惹かれた投資家がETFを購入し、結果として“企業の健全性より配当数字だけを見たマネー”が流入する形となったのです。
減配ショックから格下げへ
しかしその裏では、Telecom Italiaは以下のような根本的な課題を抱えていました:
- 競争激化による収益悪化
- 高水準の負債(レバレッジ比率が高い)
- 政府の介入により、自由な価格設定が困難に
2019年に入るとこれらの問題が表面化し、配当の減額発表が投資家の失望を呼びました。
さらに2020年には、S&PがTelecom Italiaの信用格付けを「投資不適格(ジャンク)」水準に引き下げ。これにより、多くの機関投資家がポートフォリオから外し、株価は短期間で30%以上の急落となりました。
高配当ETFの罠:構成銘柄の質までは見ていない
ETFの中には、単に「過去の配当利回りが高い銘柄」を採用基準にしているものがあります。
つまり、本質的な企業価値や財務の健全性を無視した“逆指標”のような構成になっていることも少なくありません。
Telecom Italiaはまさにその典型であり、ETFという分散ツールが、逆に特定銘柄へのリスクを見えにくくしていたと言えます。
投資家への教訓:利回りの裏に潜む“警告サイン”を見逃すな
高配当が魅力的に見えるときこそ、以下のチェック項目を見落としてはいけません:
- 配当利回りが異常に高すぎないか?
- 利益の減少に対して配当性向が過剰ではないか?
- 信用格付けや負債比率に異変はないか?
- 政府規制や政策の影響を受ける業種ではないか?
これらを無視して「利回りだけ」で投資判断を下すと、Telecom Italiaのような例に巻き込まれ、ETFごとトータルリターンが大幅マイナスになることも現実に起こります。の裏にあるリスクを正しく見抜くことです。
まとめ:過去を知り、未来を掴むヨーロッパ投資戦略
ヨーロッパ投資には、日本株や米国株とは異なるリズムと論理があります。
本記事で紹介したように、テリー・スミスやノルウェー政府年金基金といった成功者たちは、欧州に根づいたブランド力や政策の波を味方につけ、長期的なリターンを実現してきました。
一方で、ソロスのイタリア国債、ウッドフォード・ファンド、Telecom Italiaなどの失敗例からは、国ごとのリスク・通貨・政治の複雑さを甘く見た代償の大きさが浮き彫りになりました。
成功と失敗の両面から学べることは明確です。
国よりも企業、数字よりも中身、過去よりも構造を見ること。
この視点を持てば、ヨーロッパ市場は恐れるべき対象ではなく、むしろ投資機会の宝庫として見えてくるはずです。
未来のポートフォリオに、ヨーロッパという選択肢をどう組み込むか。
それはあなた自身の投資哲学を深め、広げていく第一歩になるでしょう。
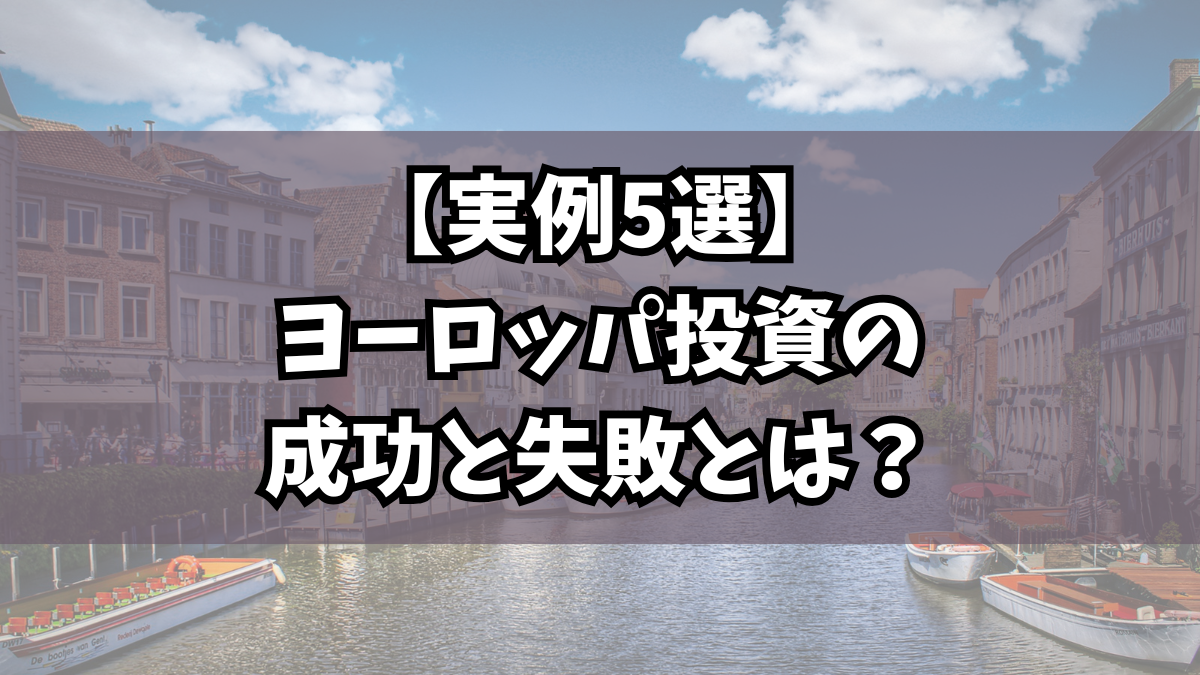

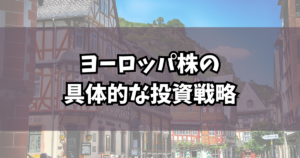
コメント